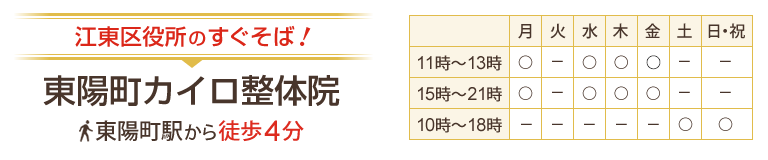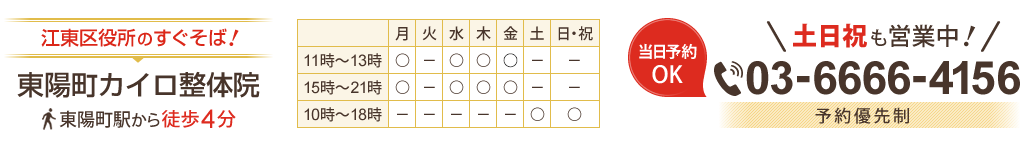膝がくっつかないO脚はなぜ?整体で変わる!その理由と効果を徹底解説
「膝がくっつかないO脚」に長年悩んでいませんか?見た目だけでなく、身体の不調を感じている方も少なくないでしょう。この記事では、あなたのO脚がなぜ膝がくっつかないのか、その根本的な「理由」をタイプ別に徹底解説します。そして、整体がそのO脚の改善にどのように効果を発揮するのか、具体的なアプローチと期待できる変化まで詳しくご紹介。諦めていた膝の隙間を改善し、健康的で美しい姿勢を取り戻すためのヒントがここにあります。
1. はじめに 膝がくっつかないO脚で諦めていませんか
鏡を見るたびに、あるいはショーウィンドウに映る自分の姿を見るたびに、膝の間に大きな隙間があることにため息をついていませんか。膝がくっつかないO脚は、多くの方が抱える見た目の悩みであり、時に「もう治らない」と諦めてしまっていませんか。
しかし、その悩みは見た目だけの問題ではありません。膝が離れていることで、歩き方や姿勢のバランスが崩れ、膝や腰への負担が増している可能性もあります。長時間の立ち仕事や歩行で疲れやすさを感じたり、特定の部位に痛みが生じたりすることはありませんか。これらはO脚が引き起こす身体の不調の一端かもしれません。
この記事では、あなたが抱える膝がくっつかないO脚の根本的な理由を深く掘り下げ、そして整体がどのようにその状態を改善へと導くのかを徹底的に解説いたします。諦める必要はありません。あなたのO脚が改善に向かうための具体的なヒントと希望を、ここに見つけてください。
2. 「膝がくっつかないO脚」のタイプ別特徴とセルフチェック
膝がくっつかないO脚と一言で言っても、その状態や原因は人それぞれ異なります。ご自身のO脚がどのタイプに当てはまるのかを知ることは、効果的な改善策を見つけるための第一歩です。ここでは、代表的なO脚のタイプとその見分け方、そしてご自宅で簡単にできるセルフチェック方法をご紹介します。
2.1 内反膝とXO脚の違いと見分け方
膝がくっつかないO脚には、大きく分けて「内反膝」と「XO脚」の2つのタイプがあります。見た目の特徴が異なるため、ご自身の状態を鏡で確認してみましょう。
| 特徴 | 内反膝(典型的なO脚) | XO脚 |
|---|---|---|
| 膝の状態 | かかとを揃えても膝と膝の間に大きな隙間がある状態です。太ももからふくらはぎにかけて、全体的に外側へ湾曲しているように見えます。 | かかとを揃えると膝はくっつくか、やや内側に入りますが、足首の間には隙間ができてしまいます。太ももから膝にかけては内側に入り、膝から下が外側に湾曲しているのが特徴です。 |
| 見た目の特徴 | 膝のお皿が外側を向きやすい傾向があります。立った時に、足全体がアルファベットの「O」のように見えます。 | 膝のお皿が正面を向いているか、やや内側を向いていることがあります。立った時に、太ももから膝が「X」、膝から下が「O」のように見え、全体で「XO」の形に見えます。 |
| 原因の傾向 | 股関節が外側にねじれていたり、骨盤が開き気味であったり、足のアーチが崩れていることが考えられます。 | 股関節が内側にねじれていたり、膝から下の脛骨(けいこつ)が外側にねじれていたり、足首の過剰な回内(内側への倒れ込み)が影響していることがあります。 |
このように、膝がくっつかない状態でも、その原因となる骨格のねじれ方や筋肉のバランスは異なります。ご自身のO脚タイプを把握することで、より的確なアプローチが可能になります。
2.2 あなたのO脚タイプを簡単セルフチェック
ご自身のO脚が内反膝なのか、XO脚なのか、あるいはその混合タイプなのかを自宅で簡単にチェックしてみましょう。以下の手順で鏡の前に立って確認してください。
- 姿勢を整える
鏡の前にまっすぐ立ちます。両足のかかとを揃え、つま先も軽く揃えてください。全身が映る鏡が理想的です。 - 膝の隙間を確認する
かかととつま先を揃えた状態で、膝、ふくらはぎ、くるぶしの間にどのくらいの隙間があるかを確認します。- 膝と膝の間に大きな隙間がある場合:内反膝の可能性が高いです。
- 膝はくっつくのに、足首(くるぶし)の間に隙間がある場合:XO脚の可能性が高いです。
- 膝、ふくらはぎ、くるぶしの全てがくっつかない場合も、どちらかのタイプに分類されることが多いです。
- 膝のお皿の向きを確認する
膝のお皿がどの方向を向いているかを確認します。- 膝のお皿が外側を向いている:股関節が外側にねじれている可能性があります。
- 膝のお皿が正面かやや内側を向いている:股関節が内側にねじれている可能性があります。
- ふくらはぎのラインを確認する
ふくらはぎの最も膨らんでいる部分が、外側に張り出しているか、内側に張り出しているか、あるいは均等かを確認します。内反膝では外側に張り出し、XO脚では膝から下が外側に湾曲しているように見えやすいです。 - 靴の減り方を確認する
普段履いている靴の底を見て、どの部分が特にすり減っているかを確認します。- 靴底の外側が強くすり減っている:O脚の傾向が強い可能性があります。
- 靴底の内側が強くすり減っている:足首が内側に倒れ込む「過回内」の傾向があり、XO脚に影響していることがあります。
これらのチェックを通じて、ご自身のO脚がどのような特徴を持っているのか、ある程度の見当をつけることができます。ご自身のO脚タイプを把握することは、その後の改善アプローチを考える上で非常に重要です。
3. あなたの膝がくっつかないのはコレが原因 根本的な理由を徹底解説
膝がくっつかないO脚は、単に見た目の問題だけではありません。実は、身体の様々な部位のバランスが崩れることで引き起こされる、複雑なメカニズムの結果なのです。ここでは、あなたのO脚の根本的な原因について、詳しく解説いたします。
3.1 骨盤の開閉と股関節の内旋外旋
O脚の根本原因として、骨盤の歪みと股関節のねじれは非常に深く関わっています。骨盤は体の土台であり、その傾きや開き具合が、股関節の動きに直接影響を及ぼします。
例えば、骨盤が後傾し、仙骨が後方へ倒れることで、股関節が外側に開いた状態(外旋位)になりやすくなります。この状態では、大腿骨が外側に開き、膝が外向きになり、結果として膝と膝の間に隙間ができてしまいます。また、骨盤の開きが大きいと、股関節の安定性が損なわれ、無意識のうちに膝が外側に逃げるような歩き方になることもあります。
さらに、股関節の「内旋」と「外旋」のバランスも重要です。膝がくっつかないO脚のタイプによっては、股関節が過度に外旋していることが原因となる場合もあれば、一見O脚に見えても、実は股関節が内旋し、脛骨が外旋しているという複雑なねじれ(XO脚タイプに多い)が原因であることもあります。これらのねじれは、日頃の座り方や立ち方、歩き方といった生活習慣によって徐々に形成されていきます。
3.1.1 骨盤と股関節の連動によるO脚の原因
| 要因 | 具体的な状態 | 膝への影響 |
|---|---|---|
| 骨盤の後傾・開き | 骨盤が後ろに傾き、左右に開いている状態 | 股関節が外旋しやすくなり、大腿骨が外に開き、膝の隙間が広がる |
| 股関節の過度な外旋 | 太ももの骨(大腿骨)が外側にねじれている状態 | 膝が外側を向き、膝同士がくっつかなくなる |
| 股関節の内旋と脛骨の外旋(XO脚タイプ) | 股関節は内側にねじれ、膝下(脛骨)が外側にねじれている状態 | 膝は内側を向くが、膝下が外に開き、膝がくっつかない |
3.2 足底アーチの崩れと足首の連動性
O脚の原因は、膝や股関節だけでなく、足元からきていることも少なくありません。足裏には、衝撃を吸収し、バランスを保つための3つのアーチ(内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチ)があります。この足底アーチが崩れると、足首の動きに異常が生じ、それが膝へと連鎖的に影響を及ぼすのです。
特に多いのが、扁平足です。扁平足は、内側縦アーチが低下し、足裏が平らになった状態を指します。扁平足になると、歩行時や立位時に足首が内側に過度に倒れ込む「過回内」という状態になりやすくなります。この過回内が起こると、脛骨(すねの骨)が内側にねじれ、そのねじれが膝関節を介して大腿骨(太ももの骨)の外旋を引き起こすことがあります。結果として、膝が外側に開き、O脚を悪化させる原因となるのです。
また、足首の柔軟性の低下や、足関節を安定させる筋肉の機能不全も、O脚に影響を与えます。足首の動きが硬かったり、不安定だったりすると、地面からの衝撃をうまく吸収できず、その負荷が膝や股関節に直接伝わり、アライメントの崩れを助長してしまうのです。
3.3 深層筋と表層筋のバランスの乱れがO脚を悪化させる
私たちの体には、骨格を支える深層筋(インナーマッスル)と、大きな動きを生み出す表層筋(アウターマッスル)があります。この深層筋と表層筋のバランスが崩れると、O脚の直接的な原因となるだけでなく、既存のO脚をさらに悪化させてしまいます。
O脚に関わる主な筋肉としては、お尻の筋肉(中臀筋、大臀筋)、太ももの内側の筋肉(内転筋群)、太ももの外側の筋肉(大腿筋膜張筋、外側広筋)、そして体幹を支える筋肉などがあります。
- 内転筋群の機能低下:太ももの内側にある内転筋群は、膝を閉じる役割を担っています。この筋肉が弱化すると、膝を内側に引き寄せる力が弱まり、膝が外側に開きやすくなります。
- 中臀筋の機能不全:お尻の側面にある中臀筋は、股関節を安定させ、骨盤の傾きを制御する重要な筋肉です。この筋肉が弱くなると、歩行時に骨盤が不安定になり、膝が外側に流れるような動きを助長します。
- 大腿筋膜張筋や外側広筋の過緊張:太ももの外側にあるこれらの筋肉が過度に緊張し硬くなると、大腿骨を外側に引っ張り、膝を外向きに固定してしまうことがあります。
これらの筋肉のアンバランスは、特定の筋肉が過剰に働きすぎたり、逆に十分に機能しなかったりすることで生じます。例えば、座りっぱなしの生活や運動不足は、深層筋の弱化を招きやすく、代わりに表層筋に頼りすぎることで、筋肉の硬さやアンバランスが進行し、O脚を悪化させる要因となるのです。
4. 整体が「膝がくっつかないO脚」に効果的な理由
膝がくっつかないO脚は、単に見た目の問題だけではなく、身体の様々な部分に負担をかけ、不調を引き起こす原因となります。整体では、このO脚の根本的な原因に対し、専門的なアプローチで働きかけ、改善へと導きます。ここでは、整体がなぜ「膝がくっつかないO脚」に効果的なのか、その理由を詳しく解説いたします。
4.1 骨格と関節の専門的なアライメント調整
膝がくっつかないO脚の多くは、骨盤、股関節、膝関節、そして足関節といった下半身の骨格と関節の連動性の乱れによって引き起こされます。これらの関節が本来あるべき位置からずれていたり、動きに制限があったりすると、膝は外側へと開いてしまい、O脚の状態が固定されてしまうのです。
整体では、まずお客様一人ひとりの身体の状態を丁寧に評価し、どの関節にどのような歪みが生じているのかを特定します。そして、熟練した手技を用いて、これらの関節一つひとつのアライメント(配列)を専門的に調整していきます。例えば、以下のような調整を行います。
| 主要な関節 | O脚での主な状態 | 整体でのアプローチ |
|---|---|---|
| 骨盤 | 前傾や後傾、左右の傾き、開き | 骨盤の歪みを整え、土台を安定させます |
| 股関節 | 内旋(内側にねじれる) | 股関節の可動域を広げ、外旋(外側に開く)を促します |
| 膝関節 | 内反(内側に曲がる)やねじれ | 膝の向きを整え、負担を軽減します |
| 足関節 | 回内(足首が内側に倒れる)やアーチの崩れ | 足首のバランスを整え、足底アーチをサポートします |
このような専門的な骨格調整により、関節への不必要な負担が軽減され、下半身全体のバランスが整います。これにより、膝が内側に入りやすくなり、O脚の改善へと繋がるのです。
4.2 筋肉の緊張と弛緩のバランス回復
骨格の歪みは、それに伴って筋肉のアンバランスを引き起こします。O脚の場合、特定の筋肉が過度に緊張して硬くなり、反対に別の筋肉が弱化してうまく機能しなくなっていることがよくあります。例えば、太ももの外側の筋肉や股関節の内転筋が硬くなりすぎている一方で、お尻の筋肉(中臀筋など)や太ももの内側の筋肉が弱くなっているケースが多く見られます。
整体では、これらの筋肉の状態を細かく確認し、手技によって硬くなった筋肉を丁寧に緩め、柔軟性を取り戻します。同時に、機能が低下している筋肉に対しては、適切な刺激を与えることで活性化を促し、本来の働きを取り戻せるようにサポートいたします。筋肉のバランスが整うことで、骨格を安定させる力が強化され、調整された関節の位置を維持しやすくなります。
また、筋肉の緊張が和らぐことで、血行が促進され、身体全体の巡りが良くなる効果も期待できます。これにより、筋肉の回復力が高まり、O脚改善に向けた身体の土台がより強固なものとなるでしょう。
4.3 姿勢と重心の再教育でO脚を改善
骨格と筋肉の調整は、O脚改善の第一歩ですが、その効果を長期的に維持するためには、日常生活での身体の使い方を見直すことが不可欠です。私たちは無意識のうちに、O脚を悪化させるような姿勢や歩き方の癖を持っていることが少なくありません。例えば、足の外側に体重をかける癖や、膝を曲げて立つ癖などが挙げられます。
整体では、施術によって整えられた身体の状態を、お客様ご自身が意識して維持できるよう、正しい姿勢と重心の位置を「再教育」します。具体的には、以下のような指導を行います。
- 足裏全体で均等に地面を捉える感覚
- 骨盤を立て、背筋を伸ばした正しい立ち方
- 膝をまっすぐ前に出し、かかとから着地する正しい歩き方
- 座る際の骨盤の位置と姿勢
これらの指導を通じて、お客様はご自身の身体の感覚を研ぎ澄ませ、無意識のうちにO脚を悪化させていた習慣を改善することができます。身体が正しい使い方を「学習」することで、調整された骨格や筋肉のバランスが維持されやすくなり、O脚の再発防止にも繋がります。整体は、単に歪みを整えるだけでなく、お客様がご自身の力でO脚を改善し、健康な身体を維持するためのサポートと教育を提供するものと言えるでしょう。
5. 整体で変わる 膝がくっつかないO脚改善のビフォーアフター
膝がくっつかないO脚に長年悩んでこられた方にとって、整体で本当に改善するのか、どのような変化があるのかは、最も気になる点ではないでしょうか。ここでは、整体施術によって得られる具体的なビフォーアフターの変化を、見た目の改善と身体の機能的な改善という二つの側面から詳しく解説いたします。
5.1 見た目の変化 膝の隙間とふくらはぎのライン
整体によるO脚改善は、まずご自身の目で確認できる見た目の変化として現れます。特に、膝がくっつかないことで生じていた膝の隙間や、ふくらはぎの不自然なライン、太ももの外張りなどが、施術を重ねるごとに徐々に改善されていく様子を実感できるでしょう。
以下に、代表的な見た目の変化をまとめました。
| 項目 | O脚の状態(ビフォー) | 整体改善後(アフター) |
|---|---|---|
| 膝の隙間 | 膝と膝の間に大きな隙間があり、内側に重心が入りにくい状態です。 | 膝の隙間が目立たなくなり、自然と膝が近づくようになります。 |
| ふくらはぎのライン | ふくらはぎの外側が張り出し、内側がへこんで見えるなど、不自然なラインになっています。 | ふくらはぎの外張りが減少し、全体的にすっきりとした、まっすぐなラインに近づきます。 |
| 太ももの外張り | 太ももの外側が張って見え、下半身が大きく見えることがあります。 | 太ももの外張りが和らぎ、内側の筋肉も使いやすくなることで、よりバランスの取れた脚のラインになります。 |
| 全体の姿勢 | 猫背気味になったり、反り腰になったりと、姿勢全体のバランスが崩れていることがあります。 | 骨盤や背骨の歪みが整うことで、自然と背筋が伸び、美しい姿勢へと導かれます。 |
これらの見た目の変化は、単に美しさだけでなく、身体の重心が正しい位置に戻り、全身のバランスが整った証拠でもあります。
5.2 身体の機能的改善 歩行と膝の痛みの軽減
見た目の変化だけでなく、整体によるO脚改善は、日々の生活における身体の機能的な改善にも大きく貢献します。特に、O脚が原因で生じていた歩行の不安定さや膝の痛み、疲れやすさなどが軽減されることで、より快適な日常生活を送れるようになるでしょう。
以下に、代表的な機能的改善をまとめました。
| 項目 | O脚の状態(ビフォー) | 整体改善後(アフター) |
|---|---|---|
| 歩行 | 歩くときに膝が外側に開いたり、足の裏全体が接地せず、特定の場所に負担がかかりやすい状態です。 | 足がまっすぐ前に出るようになり、スムーズで安定した歩行が可能になります。 |
| 膝の痛み | O脚によって膝の内側や外側に過度な負担がかかり、慢性的な痛みを抱えていることがあります。 | 膝にかかる負担が均等になることで、痛みが軽減され、快適に動けるようになります。 |
| 疲れやすさ | 身体のバランスが崩れているため、少し歩いただけでも足や腰が疲れやすいと感じることがあります。 | 正しい姿勢と重心で動けるようになるため、身体への負担が減り、疲れにくくなります。 |
| 身体のバランス | 片足立ちが苦手だったり、ふらつきやすいなど、身体のバランスが不安定な状態です。 | 足底から骨盤、脊柱までが整うことで、全身のバランス感覚が向上し、安定した動作が可能になります。 |
これらの機能的な改善は、O脚によって制限されていた活動範囲を広げ、より質の高い生活を送るための大きな一歩となります。膝がくっつかないO脚は、見た目だけでなく、身体の機能にも深く関わっているため、整体による根本的なアプローチが非常に有効です。
6. 整体施術後のアフターケアと再発防止策
整体での施術によって、膝がくっつかないO脚の根本的な原因にアプローチし、骨格や筋肉のバランスが整えられました。しかし、その効果を一時的なものにせず、長期的に維持していくためには、施術後のアフターケアと再発防止策が非常に重要になります。ご自身の身体と向き合い、日々の生活の中で意識を変えていくことが、O脚の根本改善へと繋がるのです。
ここでは、整体で得られた良い状態を定着させ、O脚の再発を防ぐための具体的な方法について解説いたします。
6.1 自宅でできる簡単なエクササイズ
整体で整った骨格と筋肉のバランスを、ご自身の力で維持し、さらに改善を促すためには、自宅で手軽にできるエクササイズが効果的です。継続することで、身体の正しい使い方を再教育し、O脚になりにくい身体づくりを目指しましょう。
6.1.1 股関節の柔軟性を高めるストレッチ
O脚の方の多くは、股関節の動きが硬くなっていたり、内旋傾向が強かったりすることが考えられます。股関節の柔軟性を高めることで、膝の向きを正しい位置に導き、膝がくっつかない状態の改善をサポートします。
| エクササイズ名 | 目的 | 簡単なやり方 |
|---|---|---|
| 開脚ストレッチ | 股関節の内旋抑制、柔軟性向上 | 床に座り、両足の裏を合わせて膝を開きます。かかとを身体に引き寄せ、膝を床に近づけるように意識してゆっくり伸ばします。 |
| 股関節回し | 股関節の可動域拡大 | 仰向けに寝て片膝を立て、股関節から大きく円を描くように脚を回します。内回し、外回し両方行いましょう。 |
6.1.2 内転筋を鍛えるエクササイズ
膝がくっつかないO脚の方にとって、太ももの内側にある内転筋の筋力不足は、膝が外側に開いてしまう大きな要因の一つです。この筋肉を強化することで、膝を内側に引き寄せる力を養い、膝の隙間を改善へと導きます。
| エクササイズ名 | 目的 | 簡単なやり方 |
|---|---|---|
| ボール挟み | 内転筋の強化 | 仰向けに寝て膝を立て、膝の間にクッションや柔らかいボールを挟みます。息を吐きながら膝で強く挟み込み、5秒キープします。 |
| サイドライイングレッグリフト | 内転筋と股関節の安定性向上 | 横向きに寝て、下側の脚を伸ばし、上側の脚を曲げて前に置きます。下側の脚を床からゆっくり持ち上げ、ゆっくり下ろします。 |
6.1.3 お尻の筋肉を活性化させるトレーニング
お尻の筋肉、特に中臀筋は、股関節の安定性を高め、骨盤の傾きや股関節の内旋を制御する上で非常に重要な役割を担っています。この筋肉を活性化させることで、O脚の根本的な改善に繋がり、歩行時の安定性も向上します。
| エクササイズ名 | 目的 | 簡単なやり方 |
|---|---|---|
| ヒップリフト | お尻全体の強化、骨盤の安定 | 仰向けに寝て膝を立て、足は肩幅に開きます。息を吐きながらお尻を持ち上げ、肩から膝まで一直線になるようにキープします。 |
| クラムシェル | 中臀筋の強化、股関節の外旋改善 | 横向きに寝て膝を曲げ、かかとを揃えます。上側の膝をゆっくり開いていき、お尻の筋肉を意識して閉じます。 |
6.1.4 足裏のアーチをサポートする足指運動
足底アーチの崩れは、足首から膝、そして骨盤へと連動し、O脚を悪化させる一因となります。足指をしっかり使うことで、足裏のアーチをサポートし、足元からのO脚改善を目指します。
| エクササイズ名 | 目的 | 簡単なやり方 |
|---|---|---|
| タオルギャザー | 足指の機能改善、足底アーチの強化 | 床にタオルを広げ、かかとを床につけたまま、足指だけでタオルをたぐり寄せます。 |
| 足指じゃんけん | 足指の独立した動きの練習 | 足指で「グー」「チョキ」「パー」の形を作ります。特に「パー」で指をしっかり開くことを意識しましょう。 |
6.2 日常生活でのO脚予防のポイント
整体で身体が整っても、日々の生活習慣がO脚を悪化させる原因となっている場合、再発のリスクが高まります。普段の立ち方、座り方、歩き方、靴選びなど、何気ない習慣を見直すことが、O脚予防の鍵となります。
6.2.1 正しい姿勢の意識
立ち方や座り方一つで、膝や股関節への負担は大きく変わります。整体で整えられた骨盤や股関節の位置を意識し、正しい姿勢を心がけましょう。
- 立ち方
膝を軽く緩め、つま先と膝が常に同じ方向を向くように意識します。重心は足裏全体に均等にかかるように立ち、左右どちらかの足に体重を偏らせないようにしましょう。
- 座り方
骨盤を立てて座り、背筋を伸ばします。脚を組む癖は、骨盤の歪みを引き起こし、O脚を悪化させる原因となるため、意識的にやめるようにしましょう。
6.2.2 歩き方の見直し
歩き方は、膝への負担やO脚の進行に大きく影響します。正しい歩き方を身につけることで、身体全体のバランスを整え、O脚の改善を促します。
- 足の着地
かかとから着地し、足裏全体で重心を移動させ、最後に親指の付け根で地面を蹴り出すように歩きましょう。
- 膝の向き
歩く際に膝が内側に入り込まないように、常に膝とつま先が正面を向くように意識してください。
6.2.3 靴選びの重要性
足元は、身体の土台です。足に合わない靴や不安定な靴は、足底アーチの崩れや足首の歪みを引き起こし、O脚に悪影響を与えます。O脚予防のためには、適切な靴選びが不可欠です。
- クッション性と安定性
足への衝撃を吸収し、足元をしっかりサポートしてくれる、クッション性と安定性のある靴を選びましょう。
- サイズと形
ご自身の足のサイズや形に合った靴を選び、足が靴の中で遊びすぎたり、逆に締め付けすぎたりしないように注意しましょう。ヒールの高い靴や底の薄い靴は、足や膝に負担をかけるため、日常使いは避けることをおすすめします。
6.2.4 身体の冷え対策
身体が冷えると、筋肉が硬直しやすくなり、血行も悪くなります。特に下半身の冷えは、股関節や膝周りの筋肉の柔軟性を低下させ、O脚を悪化させる要因となることがあります。身体を温めることで筋肉の緊張を和らげ、O脚改善をサポートしましょう。
- 入浴
シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行を促進し、筋肉の緊張をほぐします。
- 服装
特に寒い時期は、下半身を冷やさないように、温かい服装を心がけましょう。腹巻きやレッグウォーマーなども効果的です。
7. まとめ
膝がくっつかないO脚は、骨盤や股関節の歪み、足底アーチの崩れ、筋肉のアンバランスなど、複数の根本原因が複合的に絡み合って生じます。整体では、これらの複雑な要因に対し、専門的なアプローチで骨格や関節、筋肉のバランスを整え、根本的な改善を目指すことが可能です。見た目の変化だけでなく、歩行の安定や膝の痛みの軽減といった機能的な改善も期待できます。施術後のセルフケアや正しい姿勢を意識することで、O脚の再発を防ぎ、健康的な体を取り戻せるでしょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。